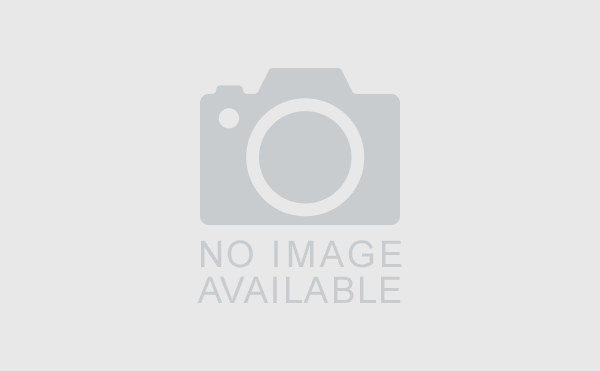岡崎邸の着工
これらの泰姫御殿建設の推進の最中に岡崎邸の着工が承認された(御目付日記天保6年(1836)1月27日の条)。そこには建物の平面と共に特記仕様が記されている。平面の記述内容は現状建物の平面と完全に一致し、現存岡崎邸の基本部分が建設当初のままであることをよく示している。
特記内容は建物の四周に庇を廻らせ、土台を総土台、屋根を取葺とするというものであった。
この総土台というのは桁行、梁間の両方向に格子状に土台を回すことを示すものと考えられるが、これは現代では当たり前であるが、武家屋敷では建物の外周のみに土台を敷く側土台が一般的だったのを格子状に敷くようにしたという意味で当時としては画期的だったものと考えられる。
鳥取市内で原形を留める武家屋敷として文政元年(1818)の棟札を持つ元福田丹波邸があるが、この屋敷では側土台に中引土台が挿入されており、これが総土台構えの前身と考えられ、土台を総土台に近付ける傾向があったものと考えられる。
屋根を取葺とするというのは理解が難しいが、取葺が栃葺のことを指すと考えると岡崎邸の当初設計の屋根は栃板葺だった可能性がある。ただ、天保7年(1837)に屋根を瓦葺に変更されたことが御目付日記に記されている。岡崎邸は竣工間近になって屋根仕様を変更したものと考えられるが、その下地はヒノキの薄板による杮葺であり、栃葺で使われる厚板ではなかった。
岡崎邸の瓦葺には極めて特殊な煙抜瓦が採用されており、屋根を瓦葺とすることはかなり早くから検討されていたが、この煙抜瓦の試作に時間を要し、仕様決定が遅れた可能性がある。
岡崎平内可之は江戸藩邸の大工棟梁に泰姫御殿建設の大工棟梁に数寄屋普請に慣れた大工棟梁、森川五郎八を加えるように伝えたことが江戸家老日記天保7年11月19日の条に記されている。
これは岡崎邸の工事が概ね完了した頃のことで、この大工棟梁は岡崎邸の工事に関与していたものと推測される。
天保8年4月、可之、家老池田能登之純と共に江戸に赴いた。
天保8年6月19日、可之、鳥取への帰国願い
天保8年6月21日、藩主、泰姫御殿工事準備完了の祝宴開催
天保8年6月23日、可之、江戸を出立
天保8年9月、池田能登之純急逝
天保8年11月、鵜殿藤輔が、泰姫様引移御用懸に任じられた
天保8年12月、泰姫御殿斧始め
天保11年、可之、引退伺いのため息子同伴で登城
天保11年12月3日、泰姫様住居竣工、江戸藩邸にて藩主と泰姫結婚式挙行
天保12年1月、泰姫様住居普請大栄出精、可之、禄高500石となる
天保12年(1841)5月16日、藩主斉訓病没
天保13年、泰姫江戸城に戻る
天保13年(1842)、藩主慶行、12代将軍徳川家慶の前で元服
天保13年(1842)10月、5代岡崎平内可之引退、家督を6代岡崎平内千尋に譲る
天保14年(1843)1月4日、泰姫逝去
彼の藩財政における才気煥発かつ緻密な采配が高く評価されていたことは、特記すべきことと言えよう。日野での鉱山経営の経験を山林資源の経営全般に活かした。藩の大変厳しい財政状況の改善を見た。これも、大雨、長雨で洪水をも伴う天保2年(1831)に始まり、天保7年(1836)にピークを迎える大飢饉の中で成果を示し得たというのは驚くべきことだ。
鳥取池田家は、若い藩主、斉訓と将軍家斉の末娘、泰姫との婚姻を準備する上で焦眉の課題は泰姫の住む御殿の建設であった。泰姫御殿を姫の最愛の父、将軍の住まう城のすぐ近くに建設することであり、その実施計画の作成とその試作を秘密裏に行うことを岡崎平内に委任した。私たちは今、天保5年(1834)にいます。
岡崎平内は、棟梁、森川五郎八の助力を得て、この特殊な使命に取組んだが、彼の本来の視座、藩財政の復興を忘れることはなかった。このために彼は、先ず、藩内の木材ストックの調査を綿密に行い、鳥取の木材を江戸に送り、これを販売して、建設経費を補填しようと考えた。火事は、江戸の華とも言われたが、大木材消費地であり、絶えず需要が生まれ、鳥取の林業振興効果が期待される。
岡崎平内は、加えて、泰姫御殿を高価なヒノキの四方柾で建てるのでなく、鳥取のスギを用いることを第一とした。藩の山林は、戦国時代に荒廃した山林に植林を始めて未だ2世紀しか経っておらず、芯去四方柾材として使うには断面が不足したので、鳥取のスギ芯持材を面皮仕立てとして数寄屋風の艶やかな御殿とすることを提案した。
また、材の標準化を行い、長材を要する部材についても、単一部材としなければならない部材を厳選し、現場で継いで使える範囲を最大限広げ、搬送性の良い標準部材の採用を最大限にする構法を提案した。
このようにして建設費用は1/10に削減できるが、果して将軍、殊に大奥から来る腰元達の眼に適う御殿となるか否かが課題となり、試作建物で確認することとなった。
1836年に、武家屋敷として着工されたのが、現岡崎家住宅である。この建物には更に特別の工夫が見られるので、それらについては、後述する。武家町に位置し、大きな長屋門と土塀で囲まれていた。
屋敷には3棟の蔵(米蔵、味噌蔵と日用家財用)もあった。
天保7年(1836)には恐らく竣工していたものと思われるが、岡崎平内は、江戸藩邸に泰姫御殿の大工棟梁の一人として森川五郎八を雇用するよう提案した。この大工棟梁は、神田佐久間町に店を構える江戸の材木御用商人、森川五郎右衛門の弟であったが、可之が江戸に送った木材の管理を依頼したのは、この材木商であったように思われる。この提案の翌年、天保8年(1837)には岡崎平内は、鳥取藩普請奉行である家老、池田能登之純と共に江戸に赴くこととなった。
泰姫御殿の工事には3年ほどの期間を要し、天保12年(1841)に結婚式が挙行されるとこの御殿建設事業の成果が高く評価され、家禄が500石となった。
第6代岡崎平内千尋
天保13年(1842)10月、家督相続 500石
嘉永6年(1853)7月、幌御預 礼席順席
安政4年(1857)8月、軍式御用
文久元年(1861)1月、御使番軍式方頭取助役兼帯
文久2年(1862)8月、武器奉行軍式方頭取兼帯
文久3年(1863)12月、軍式方頭取昵近
元治元年(1864)7月、元〆役 産物会所銀札場長役兼帯
明治元年(1868)1月、軍式方頭取小姓頭兼帯 元〆役銀札場長役兼帯
明治元年(1868)3月、元〆役銀銀札場長役御免伺 元〆役銀札場長役兼帯仰付
明治2年(1869)4月、池田但馬守付人仰付 但馬守在所福本詰め
第7代岡崎平内可観
明治2年(1869)、版籍奉還によって藩主は、華族に、武士は、士族となった。
明治4年(1871)、廃藩置県によって鳥取藩は、鳥取県となった。
明治6年(1873)、秩禄処分によって家禄は廃止され、士族には僅かな公債が支給されるのみとなった。
また、廃刀令と国民皆兵の徴兵制の施行によって軍事職をも失い、士族は、実質的に失職した。
明治7年、第7代岡崎平内可観、板垣退助等の愛国公党に入党
明治9年(1876)、鳥取県が島根県に併合された
明治10年(1877)、第7代岡崎平内可観、陸軍省に入省も短期で退職
明治10年(1877)、共立舎に入会し、士族の救済、機織りなど殖産興業に努める。
明治10年頃、愛護会を開設
明治12年(1879)、第7代岡崎平内可観、島根県会議員となる。
明治14年(1881)3月、第7代岡崎平内可観、島根県会議長となる。
明治14年9月、鳥取県の独立(鳥取県の再置)を達成。
明治15年1月~明治17年3月、第7代岡崎平内可観、鳥取県初代県会議長となる。
明治22年(1889)11月~明治23年(1890)5月、第7代岡崎平内可観、初代鳥取市長となる。
明治23年(1890)11月~明治24年(1891)7月、第7代岡崎平内可観、衆議院議員となるが、短期で辞職。
移住武士多く、第7代岡崎平内可観、近隣武家屋敷購入。
武道場、双樅館創設、雖井蛙流指南。
賀露港修築計画に伴い、修築に必要な岩石の切り出し場とするべく賀露荒神山に持っていた別荘を引き払い、購入した隣地に移築し、隠居小屋とした。
明治29年(1896)9月、第7代岡崎平内可観、西伯郡長となる。
明治32年(1899)頃、第7代岡崎平内可観、岩美郡長となる。
岩美の網代港の修築計画を検討。
大正6年(1917)、逝去