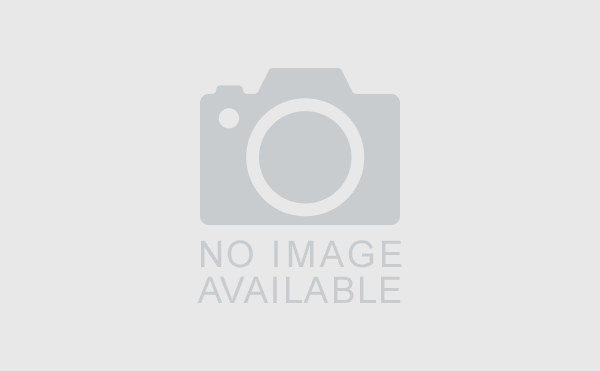岡崎平内が目指し、実践した議会制民主主義の下での地方振興 その2
国政に参加
当時、岡崎平内は、議会制民主主義に全幅の信頼を置いていた。
これが正しく回るなら必ずや日本国の繁栄が生まれると確信していた。
岡崎平内は、鳥取県再置と共に鳥取県令から邑美・法美・岩美郡長を命じられたが、明治14年12月25日、新たに鳥取県会が開設されると郡長を辞し、鳥取県会議員に立候補し、県会議員となった。更に、明治15年1月27日、第1回 の議会で議長に選ばれた。
彼は、島根県会で提案した議事細則にかなり自信を持っており、それが議会制民主主義を推進する上で必要不可欠と考えていたようで、島根県で成立した議事細則を取り寄せ、これを鳥取県から鳥取県会に提案させ、逐条審議し、成立させた。
岡崎平内は、鳥取県会議長を2期務めたが、明治17年4月からは鳥取県邑美(おうみ)・法美(ほうみ)・岩美郡長として鳥取での産業振興、教育体制・医療福祉体制の整備と共に県令の推進する道路整備・港湾整備に協力を惜しまなかったが、併せて自邸に武道場をつくり武道の振興に勤しんだ。
明治22年11月1日、鳥取に市町村制が敷かれると彼は鳥取市長に担ぎ出され、着任したが、鳥取県が東伯・西伯郡長を依頼し、双方を兼務した。岡崎平内は、この鳥取市においても市議会に鳥取県会で成立を見た議事細則を提案し、成立させた。彼は、同じ議論を、島根県会、鳥取県会と鳥取市議会とで都合3回行ったことになる。彼は、この議事細則を議会制民主主義の根幹と考え、自信を持っていたと考えられる。
しかし、彼の鳥取市政は極めて短期であった。明治22年2月11日に公布された大日本帝國憲法と同時に公布された衆議院議員選挙法によって明治23年7月1日に衆議院議員の総選挙が行われた。
この結果、全国から総数300人の議員が選出され、鳥取県から岡崎平内、山瀬幸人、松浦宏雅の3名が選出された。岡崎平内も松浦宏雅も、思想的には中立であったが、多くの無所属議員と共に院内会派の大成会に属した。山瀬幸人は、同じく無所属であり、院内会派にも入会しなかった。
明治23年11月29日に最初の会議が開催された。
時の首相は、参議として山陰巡視を行い、その帰朝報告に鳥取県再置を提案し、鳥取県再置を実質的に決めた山県有朋であった。
山県有朋の施政方針演説は、12月6日に行われた。
しかし、板垣退助党首の立憲自由党や大隈重信党首の立憲改進党らの反政府勢力が多数を占め、山県内閣は、衆議院における法案や予算案の審議で苦労を重ねることとなった。
明治7年に民撰議院設立建白書を認め、自由民権運動の旗頭と考えられていた板垣退助が、自由民権を具現化した国会において鳥取県の再置を実現し、地方自治を推進しようとする山県有朋と対立する様は岡崎平内にとって驚きであった。
実は、岡崎平内は、慶応4年3月5日、境直衝体分隊長として板垣退助の率いる迅衝隊のサポーターとして甲府城入城を果たし、3月6日には近藤勇の率いる甲陽鎮撫隊と甲州勝沼で合戦し、これを共同で撃破した。
このため岡崎平内は、板垣退助に親近感を持ち、板垣退助が明治7年に設立した愛国公党にも入党し、岡崎平内の設立した愛護会は、この愛国公党の鳥取版という意識があったのであるから岡崎平内としては山県有朋と板垣退助が仲良く話し合う場が国会であるべきであった。現実は、この両者が単に対立している様を見て議会制民主主義が未成熟であるからこのような事態に陥ったと考えたのであろう。
地方政治へ
岡崎平内は、7月11日に衆議院議員を次の辞任の弁を残して辞職した。
「帝国議会は詐謀の士、狂暴の壮士のために愚弄され、嚇怒され、議員は徒らに口角の紛争をなすに過ぎず、故に神聖の議決も国会の意志には非ず。
然れども国会の罪には非ずして時勢の然らしむもの、政府人民の感情を異にし相反目するの久しきこれを致せり。
これを救治して大いに国家人民の将来の大計を樹つるは至難の業、おのれその器にあらず。宜しく退きて代うるに堪能の士を以てせん。」
議会制民主主義が未成熟であると認識したが、議会制民主主義自体が悪いとは考えなかった。
以降、岡崎平内は西伯郡長、岩美郡長を歴任すると共に共立社を核として鳥取の各種の産業振興を推進し、県や市の教育環境の整備・港湾整備に協力し、県政・市政の健全化に努めた。
彼の後、県議会議長や市長となった人々の多くは愛護会のメンバーであり、県政・市政における彼の影響は長く続いた。
彼はこれと共に自宅に剣術道場「双樅館」を設立し、因幡鳥取藩秘伝の剣術、雖井蛙流(せいありゅう)の継承・普及に努めた。岡崎家代々伝来の免状が多いというが、岡崎平内が受け取った免状として確認されるものは次のようなものである。
慶応元年6月 水練神伝流兵法初段免状皇朝水軍宗師徳布家
明治16年12月9日 八條流当流初伝之秘事 箕浦貞太郎元行
明治23年5月 雖井蛙流平法利集巻 加藤鄭美
明治26年申5月 雖井蛙流平法夢想秘極之巻 河合與七郎元寿
明治28年8月 馬術 遠馬秘傳集 箕浦貞太郎元行
明治29年5月 雖井蛙流平法夢想秘極巻 宮崎貞蔵正功
明治29年5月 雖井蛙流平法允可 深尾角馬
明治29年8月 作法之巻 箕浦貞太郎元行
明治29年8月 八條流上口面押掛馬 箕浦貞太郎元行
明治29年8月31日 八條流当流初伝之秘事 箕浦貞太郎元行
明治29年8月31日 八條流当流系伝 箕浦貞太郎元行
明治29年8月31日 神鞭之巻 箕浦貞太郎元行
明治29年8月31日 御出陣御下乗故實 箕浦貞太郎元行
明治33年庚子六月 剣術 雖井蛙流平法夢想萬勝之巻
雖井蛙流平法は、深尾角馬(1631年(寛永8年) - 1682年(天和2年))が創始した武術である。兵法ではなく平法としたのは、武士が平素から稽古すべき心得を説いているからという。その技法は、旧来の甲冑を付けた介者剣術に対して甲冑を付けない素肌剣術に改め、深尾が学んだ諸流の技への返し技で構成されている。
いわば武士の護身術のようなものであるが、ありとあらゆる剣術による攻撃に対して打ち返す武術であるから大変厳しい鍛錬を要する。
この武術は、彼の討議の仕方にも通じ、よく話しを聞き、その類似点、相違点を明らかにし、結論を導く。
岡崎平内は、双樅館において多くの弟子を育てたが、それは単に武術を鍛錬するためではなく、人々の思考・論理を明晰にすることを期待したものと考えられる。
岡崎平内は、民主主義を徹頭徹尾大切にし、それさえ出来れば地域の振興が達成され、国家が繫栄すると信じていた。この信念が鳥取県再置を実現した。