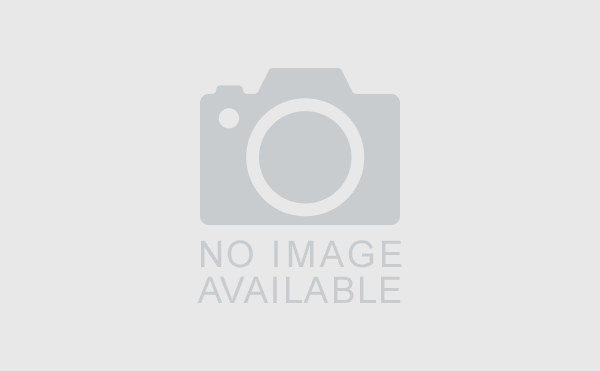奏姫御殿の建設
しかし、これらの財政復興は、主として文化・文政期に可之が行ったことである。天保2年(1832)に生まれた藩主と徳川将軍末娘泰姫との婚儀に対してこれを良い話しとして新たな財政負担に対して可之が即座に承知できたのは何故かー更に別の財源の可能性を見込んだようであるが、それは何であったのか?―
婚約決定から藩が行った婚姻準備
天保2年(1832)9月の藩主斉訓と将軍家斉の令嬢泰姫との婚約から藩は様々な検討を行ったに違いないが、表立った動きは少ない。敢えて挙げるなら天保3年(1833)に可之を順席とし、翌天保4年(1834)に100石加増により岡崎平内の家禄を300石としたことであろうか。天保4年3月7日の家老日記によれば、岡崎平内の藩財政復興が評価され、銀知100石加増によって都合300石の知行となることが伝えられた。
やや頻繁な昇給であるが、藩の判断として可之が達成した藩財政の復興の功績が高く評価されたためと考えられる。
木材業者経営実態調査
藩が行った婚姻準備と思われることは、天保4年(1834)3月17日の家老日記に記されている藩内の木材業者調査である。この家老日記には虫食い部分があり、全てを読み熟せないが、全ての木材業者がどの山からどのような木材をそれぞれどのような数量を入手し、どのような木材をどのような数量を水運によって何処に搬出しているのか、またそれはどこから受けたどのような注文に対するものだったのかなど、かなり詳細に木材流通を把握しようとするものであったものと読み取れる。
賀露港から江戸への木材送付の試行
この間、泰姫御殿の設計が進められ、必要な木材の概略の数量が判明してきたものと思われるが、この木材流通実態調査結果に基づいて泰姫御殿に使える木材の入手経路を明確にし得たのであろう、賀露から江戸に向けて多量の木材が搬出されたことが、天保5年(1835)4月24日の家老日記に記されている。
この時点では設計の概略しか決まっていなかったものと考えられるが、送付された建材の数量はかなり多い。
荷揚げ場所を鍛冶橋御門外南鍛冶町1丁目河岸としたようである。
このため江戸での荷揚げ場所を確保したようであるが、荷揚げした建材の管理を江戸の材木商に依頼せざるを得なかったものと思われる。
しかし、後に荷揚げ場所を明確にし、柵を設けたことが江戸家老日記天保7年11月18日に示されている。
鳥取藩が生れたのが、1600年(慶長5年)、池田長吉の時代からとしても藩が管理した山林では、樹齢が200年程度と若く、伐り出せる木材の樹種はヒノキでなくスギを主体とせざるを得ず、寸法も従来の御殿建築で当り前であった芯去りの四方柾で行うことは不可能であり、芯持ちの、従って割れが入り易いので背割りを入れざるを得ず、ややもすれば角に表皮の丸味が出てしまう危険性のある材を用いる必要があった。
このようなことから鳥取藩は、泰姫御殿を材の隅を面皮とし、この丸味の持つ赤見を拭き漆で強調し、切断面には墨を塗り、黒地と赤を際立たせる数寄屋風の造りとせざるを得ないと判断したようである。
江戸藩邸敷地拡張
また、姫と共に大奥から移って来る女官と男衆合わせて70名からの召使のための宿舎は基本的に二階建ての長屋として十分に快適なものとするなどと検討するも当時の鳥取藩江戸藩邸の敷地ではどうにも納まらないので、敷地の拡大を幕府に依頼せざるを得ないことが次第に明確になってきていたものと思われる。藩は、天保6年(1836)9月27日の江戸家老日記に「泰姫君様御縁組被仰出候に付而は因幡守居屋敷御住居向地所不足ニ付添地之儀奉願候」と記されるように敷地の拡張を幕府に願い出た。この伺いは、普請懸、楢村弥兵衛が行い、この江戸家老日記によれば即刻「無余儀筋ニ有之候」として承諾された。
泰姫御殿建設体制の整備
天保5年(1835)9月7日の家老日記に記されるように、可之は御櫓にて藩主から泰姫様引き移り御用懸を仰せつかった。
江戸でも天保5年(1835)12月10日の江戸家老日記に記されるように楢村弥兵衛、保坂達右衛門、加賀美隼人の3名に泰姫様御住居御普請御用懸を仰せ付けた。
更に天保6年(1836)7月27日の家老日記によれば、福家番右衛門が泰姫様御住居向御普請御用懸として江戸詰として鳥取を出立した。福家番右衛門は、岡崎平内家の親戚だったので可之としては意思疎通が容易で好都合であった。
『家老日記』天保四年三月一七日の条に次のようにある。
一材木津出し左之通可被仰付哉と御普請奉行申達候ニ付其通承届宜取計候様右同人エ申渡之
惣材木屋年中仕入之木数并山中より売払之木数夫之先例之通数類并役場エ書出させ右
根帳出来惣材木屋直津出し相(虫食い)木数半紙ニ相認メ材木御用聞より数類役エ差
出し諸〆り役申談右仕入売払之根帳ニ引合と得員数取調直津出し見計積り御普請奉行
御吟味役御目付エ申談取極メ之上右取調懸り夫々押切(虫食い)御用聞エ差(虫食い)
手形何(虫食い)相認右半紙小手形相添津出し取調(虫食い)差出し尚又根帳ニ付留
川口通手形押替致し差返し御用聞より是迄之通御材木奉行エ差出し致押切御普請奉行
御吟味役御目付夫々押切相済し御材木奉行より御用聞エ相渡可申事
但津出し川下ケ之節取調懸り下作廻材木御用聞立合相改可申事
右取調懸り諸〆り役 清水又市
数類役 石脇彦次郎一左之木品御手船御