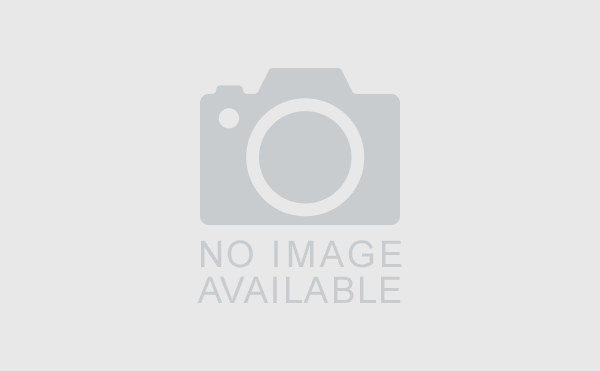岡崎邸の保存
岡崎家住宅が鳥取の歴史を刻む重要な史跡記念物として重要と考えられるのは、この第7代岡崎平内可観とその仲間、愛護会による必死の活動の結果、達成された鳥取県再置にあると言えよう。愛護会メンバーは、東京で政府要人を訪問し、鳥取県再置の嘆願を精力的に行う他、島根県令、境二郎に鳥取県分離の上申嘆願書を認めさせるなどの鳥取県再置運動の結果、山形有朋の山陰視察を生み、鳥取県再置が実現した。
鳥取の岡崎平内の屋敷は、大正13年(1924)に鳥取の豪農に譲渡され、借家とされ、日本初の女性弁護士、中田正子(1910-2002)が住むようになったのは、昭和17年(1942)頃であり、彼女は半世紀余にわたってこの屋敷を事務所兼住居とした。彼女は、鳥取県若桜町出身の社会党代議士と結婚しており、一男一女を設けていたが、岡崎家住居を自らの財産とするのを良しとせず、終生借家人としてここに住まい、91歳で亡くなった。
終戦直前の昭和18年(1943)9月10日、鳥取はマグニチュード7.2の直下型地震に見舞われ、80%の家屋が大損害を被る大変大きな地震に見舞われたが、日本帝国は戦争に継続に集中し、震災の報道も僅かで、支援もなかく、市民は自力復興を余儀なくされた。幸いにこの屋敷は殆ど損傷なく済んだが、多くの人々が居所を失い、この屋敷にも中田正子一家以外に複数の所帯が居住することとなった。
戦後、マッカーサーによる農地改革によって居住地から遠い耕作地の保有が禁じられ、豪農の生計は次第に悪化し、家賃収入がそれを補いきれなくなると岡崎家住宅は、借家人の一人に譲渡されることとなった。しかし、鳥取は昭和27年(1952)4月17日に大火に見舞われ、市街地の2/3が焼失した。この屋敷は、無事であったが、買い取った人の事業が困難となり、宅地を切り売りすることとなり、更に子供の成長に伴い手狭となったので、転居し、屋敷は不動産業者の管理するところとなり、夫に先立たれ、3人の子供も成長して鳥取を離れたので中田正子女史のみが単身住み続けることとなった。
大地震、大火と種々の経済的・社会的な災難の中で、岡崎家住宅は、老いた女性の手でほぼ原形が維持されたということは驚くべきことと言えよう。
平成14年(2002)10月、中田正子が死亡すると、完全な空家となった。
平成12年(2000)、この屋敷の保存を目指す市民グループが生まれた。
平成13年(2001)、市民グループ、岡崎邸の調査を実施。
平成20年(2008)、岡崎邸、宗教団体に転売さる。
平成21年(2009)、岡崎邸所有宗教団体、解体工事開始、市民グループ、解体中止要望、購入、応急補強工事
宗教団体は不動産業者から購入する際に通常の地価の3倍程度の値段で購入していたので、市民グループの募金活動は、全国的な支援を得て、かなり多かったが、買い取るのが精一杯であり、修繕費用を工面することができなかった。
1943年の鳥取地震の被害は甚大であったが、戦時であったため大きく報じられることもなかった。被害は、旧町人町では深刻で、旧武家町はやや軽微であったが、それでも一般には大規模な被害であった。被災者は、救援もなく、自力でやっとのことで空地にバラックを建てて寒さと飢えを凌がざるを得なかった。
このようなバラックが集積したためもあるが、1952年の大火は、鳥取駅の近傍から出火したが、外堀である袋川を簡単に越えて市街地の2/3を灰燼と化した。
このような災害にも拘らず、岡崎家住宅は、中田正子女史が住んでいたこともあり、十分に居住継続可能な良い状態を維持していた。2001年、岡崎家保存のための会が組織され、調査が始められた。
木材産業からの建築技術革新
鳥取の山林は、古くからの歴史を持つが、長い戦国時代に乱伐され、江戸期になって本格的な植林が行われるようになった。樹齢、従って100年~150年強で、十分建築用材とはなったが、狂いの少ない芯去りの四方柾材を取るにはやや若過ぎた。四方柾材は、芯を避け、どの面も直径に対して45度の角度を付けて部材を取るので、かなり太い木材からしか取れない。加えて、林地が急勾配で、長材の切り出しが難しく、殊に遠距離まで材を搬送するには一定程度材の長さも標準化する方が扱い易い。そこで、建設現場において母屋材は金輪継ぎで、足固め、胴差、桁については柱を介して雇い竿枘シャチ止で継いで長材とするシステムを構築し、材長の標準化を図り、江戸まで搬送する際の手間の軽減に努めた。
加えて、柱材を必要な断面切り切りの細い材を芯持ち材とし、背割りを入れて乾燥によるひび割れを防止するのを原則とするのに加えて隅角部の面を年輪の冬材面とする面皮仕立てとし、断面の小さな樹木でも使える技術を一般化した。このようにすると柱面は板目となるので墨で彩色し、隅角部の面皮の赤味がかった木地に漆を拭き、黒と赤のコントラストを作り、艶やかな造りとしている。この屋敷では、幕府の奢侈禁令に従って、化粧長押を省略しているが、天井の廻り縁や竿縁も面皮仕立てとして、大変艶やかな空間を生み出している。
かの有名な姫御殿に使われたとなれば、このような造りは、数寄屋造りを想い起させるに余りある。四方柾造りでは一般には生み出し得ない極めて装飾性の高い造りとなっている。
背割りは、柱の場合には通常見えない面に入れるが、この屋敷では、柱のみならず、根太や母屋といった断面の小さな、しかも見えない部材にまで使われており、芯持ち材のひび割れを大変嫌ったことを示している。
岡崎家住宅
現在は切妻造りの棟の高い住宅であるが、建設当初は四周に庇が廻らされ、入母屋風の外観であった。
岡崎家住宅は、水路の脇にあったというが、今日では水路は暗渠となっており、武家町の車がすれ違い得る道路2筋のT字交差点にあり、緑で覆われた岩山の裾で、馬場町武家町の始まりの位置にある。岡崎家住宅を示す古地図によれば、その敷地基本は、間口15間7尺、奥行21間5尺(約1,000m2)である。
明治期に鳥取の旧武士は極端に減少した。多くの旧武士は、失職し、県外に転出したので、鳥取に残り、鳥取の活性化を目指した岡崎家は県外に転出する旧武士の住宅を購入したので、岡崎家の敷地は数倍に広がった。
元々の屋敷では主屋の南にある庭師と大工の住まい兼事務所となっている長屋門を入ると、2筋の石畳の道で、一方は正面の式台玄関へ、他方は左の内玄関に向かう。家族は、更に建物の左側面にある勝手口しか使わないのが、基本であった。
敷地の北側には池があり、美しい庭が作られていた。門の右側には茶室があった。北と西には、米蔵、家財を収納する本蔵、味噌蔵の3棟の蔵が置かれ、西には野菜畑があり、新鮮な野菜と恐らくは梅や柿などの果実をつける樹木もあったに違いない。
建物の外観は、美しい伝統的な住居と変わりなく、日中は仕舞われる建物全長の雨戸の内側は縁側で次いで白い和紙を格子上に貼った明り紙障子が通常は閉められ、あるいはそよ風の吹く夏は開けられる。
式台玄関を入ると母屋を取り囲む廊下に上るが、ここは通常の廊下の倍の幅で、畳敷きとなっていた。
これを入ると三部屋の続き間に入る。先ず6畳の控えの間、次いで床の間に違い棚を備えた表座敷と最後は正面に床の間を持つやはり8畳の奥座敷となる。これら三部屋を合わせると大宴会を催すことの出来る22畳の大広間となる。この表三部屋に平行な左側、ないし西側の裏の部分は、内玄関と勝手口に連なる家族の日常生活の部分となっている。
ここで重要なのは奥座敷の更に奥の間で、納戸とも言うべき隅の間であるが、この天井には階段穴が隠されている。この部屋は、実は納戸ではなく、仏間であったようである。
この隠し階段穴を開け、予備の階段を掛けると階段室を兼ねる控えの間を経て、床の間と濡れ縁風の縁側を備えた秘密の部屋、10畳間の座敷に辿り着く。そこからは濡れ縁と控えの間までつながる大きな窓面一杯に城主の城と城山、久松山を手に取るように望むことが出来、城見の間と名付けても不思議ではない。
この室こそ、この岡崎家住宅が、鳥取池田家江戸藩邸に増築される泰姫御殿においてまだ若い泰姫が住み慣れた江戸城の中に住んでいるかのように感じさせるべく、寝所の2階に城見の間を設ける構想の試作であることを最も明瞭に示す部分である。
この2階の座敷を作るに当たって上階の人によって先祖の位牌を収めた神聖な仏間が踏まれることを避けるためと思われるが、この隠し階段の室の片隅に設けられた仏間は、この建物の主要な枠組みの外に突き出されている。
下階の三室の続き間の上は物置となっているが、その床は、吊り天井の上に別構造で床組を組んだ浮き床となっているが、これは完璧な防音工事を示している。これは上記の城見の間の床に実際の泰姫御殿で採用する床仕様を試作したものと思われる。
この建物の2階は、この城見の間を除けば、上記の続き間上も含めて物置であるが、そこへは、隠し階段、並びに城見の隠し部屋を通らずにアプローチ出来るように梯子で上り下りする穴が天井に設けられている。
この屋敷には、床の間が通常よりも多く、見栄えに特別の配慮があるように見える。同様に、控えの間と表座敷の間の欄間に収められた筬欄間は、目も細かく、かつての貴族社会を思わせる細工レベルの高さを示している。
鳥取池田家江戸藩邸に設けられた泰姫御殿は、元々の3000坪の敷地に1000坪の敷地を足して建てられたものである。鳥取の岡崎家住宅で試作されたのは、この1000坪の敷地にぎっしりと建てられた御殿の一部分に過ぎない。
無論、今日われわれが目にすることの出来る住宅は、無傷とは言えない。敷地の過半は切り売りされている。庭は無く、茶室もなく、武道場も蔵も無くなっている。一部の廊下も敷地の切り売りに伴って切り取られている。逆に西側には下屋の外に台所や浴室のための空間が増設されている。
岡崎家住宅の特徴と構造的な質の高さ
先ず、この建物が、1943年の鳥取大地震を始めとする鳥取の町を襲った数々の地震に見事に耐えたことは、特筆に値しよう。ここではその構造的な質を読むべきであろう。
社寺や御殿のように固められた地盤の上に据えられた自然石の基礎の上に柱は建てられ、それは小屋組みまで切れ目なく繋がっている。これらの柱は、3段の帯で束ねられている。最も下段はクリの土台であるが、これはその半間ほど上の床受けの足固め材と束で組とされ、やがて10倍の剛性をもった帯となっている。
同様に、襖が走る鴨居と更にその上の床受けの横架材とはやはり間に細かい格子の欄間を挟むが、やはり束で結ばれ、2部材構成の丈の高い、従って剛性の高い横架材を形成していることが読み取れる。建物の断面構成を見ると、目に触れる居住階の構造部材はスギ材でつくられているが、床面より下はクリ、小屋材はマツとなっている。
この上下の2部材構成の帯締めだけでは満足せず、柱も随所で管柱を添えて基本となっている小屋組まで通しの柱と2重化している。この通し柱と管柱の間隔は、半間程度を原則とするが、その間を床の間として使ったり、通路として使ったりしているが、基本は貫の上に竹で木舞下地を組んで土壁が塗り込まれている。
一見しただけでは判り難いが、表座敷側は裏側の座敷よりも天井を高くし、天井上には小屋組みまでの間に空間があり、鴨居から上部の軒桁までの巨大な横架材としている。この構成は、棟位置までぐるりと巻いて、固い筒を構成している。裏側の座敷も、下屋につながる位置から棟位置まで鴨居から軒桁まで全面的に壁が充填された筒を形成しており、胴差の位置が交互にずれるが、棟位置の鴨居から棟桁までの土壁の充填された大きなフレームで矛盾を解消している。城見の間が納められている部分がやや特殊であるが、構造的には表座敷から裏座敷までの母屋部分で堅固な構えを構成し、それに下屋を凭せ掛けていることが判る。上部に固いフレームを構成しているので、地震時には柱と鴨居との接合部で柱が折れる危険性があるが、これを防止しているのが、床の間の裏の耐力壁である。この耐力壁は、軸組の軸線とは半間程ずれているが、土台から立ち上げられており、地震時の建物の変形を抑制している。
このようにしてこの住宅は、極めて柔軟性の高い伝統的な仕口で全体的に同様のやり方で構成され、極めて強固に補強されており、地震入力をよく拡散させ、固過ぎたり、柔らか過ぎたり、あるいは弱過ぎる部分での損傷も見られない。このことは、この住宅が幾たびも繰り返される大惨事に耐える素晴らしい特性を有することを示している。
文化財保護の難しさ
最後の居住者であった中田正子女史は、2002年に亡くなった。この亡くなる直前にこの文化財を保護する組織が生まれ、後にこれが、NPO市民文化財ネットワーク鳥取へと発展し、岡崎家住宅を鳥取市の史跡とすることを提案している。
しかしながら、所有者であった不動産業者は、新しい布教センターを構築しようとした新興の宗教団体に売却した。保護組織は、寄付金を集めて鳥取市と協力して保存することを考えていたが、宗教団体が土壁の解体を始めたので、2009年、保護組織は急遽、単独でこの住宅を購入した。ところが、鳥取市の文化財審議会は、岡崎家住宅の歴史的価値を認定することを拒絶した。従って、最後の手段は、NPO市民文化財ネットワーク鳥取の手に残ることとなったが、寄付金は岡崎家住宅の購入でほぼ使い尽くされた。
この保護団体は、様々な方法で、寄付や住宅修理高等技能者のボランタリー、材料供給者などを募集している。
こうなると官僚の専横性に直面する日本のデモクラシーを特徴付ける日本風の住民運動を再認識する。
岡崎家住宅に適用可能なもう一つの公的保護の制度としては、景観形成重要建造物として指定することである。しかし、これは鳥取市の景観審議会が審議するものであるが、文化財審議と同様に基礎的な素養の欠け、頑固な役人の助言を受けることとなる。という訳で、岡崎家住宅は、残念なことに、購入時に壊された状態のままに置かれ、スティール・ケーブルで補強されている。大変惨めな姿を示しているので、その修復がなされないことには景観形成重要建造物と認定されるのは難しいように見える。
城はとうの昔に壊され、上記のような災害に遭って若い世代に地域の寄って立つ文化を教育するために示すべき歴史的建造物が殆どない鳥取市のぐずぐずした態度は実に理解し難い。
この保護団体は、鳥取市では明治期における旧武士の失職・移住、1943年の地震、1952年の大火などのために武家屋敷は殆ど消滅しているので、この住宅を他の文化遺産と比較して重要さを示すのは難しいと控え目に記している。
しかしながら、この住宅と比較できるもう1軒の武家屋敷、旧福田丹波家住宅があり、こちらは1818年に建てられ、丁寧に住まわれ、また、常に人が住んでいる。福田丹波家は、鳥取池田藩において大変重要な家で、家禄は3,500石であった。岡崎家住宅が建てられた際の岡崎平内の俸給は、300石であったのであるからその違いは明白である。この住宅は、城の正面にあり、普通には文化財指定が施されているべき建物である。
そう、鳥取は普通ではない。
岡崎家住宅と旧福田丹波家住宅を比較すると次のような点が挙げられる。
・岡崎邸の柱は、5.2寸角、即ち15.76cm角と一般的な武家屋敷に比して大断面、しかもそれらの柱の断面は床下では6寸角となっている。これに対して福田丹波邸の柱は、一般的な武家屋敷の場合と同じ4寸角、即ち12.12cm角である。
・岡崎邸の土台は、7寸角、即ち23.1cm角で全ての主要柱下に格子状に配され、床面位置の足固と常に一対となって柱の脚部を固めているが、福田丹波邸では5.2寸角、即ち15.76cm角で、棟筋と建物の外周と棟下の中通りのみに配されている。
・岡崎邸では1階の床の間の背の壁は、柱梁の軸線からずれているが、土台から立ち上げられ、明確に耐震壁となっているが、福田丹波邸では壁は全て足固の上で土台からは立ち上げられていない。
・岡崎邸の柱は、下屋の一部でクリを使っている以外は、全てスギの面皮造りで角の面部分は朱、切られた板面は墨塗りとして建物全体が数寄屋風の造りとなっている。この装飾的な仕様は、コスト削減の結果であることと重なる。これに対して、福田丹波邸では主座敷1室のみがスギの面皮造りとなっている。
・岡崎邸では1階の主人と家族の居室部分の天井を下げて、その上に二階に隠れ座敷を設け、階段の存在も判らないようにカモフラージュしている。
・岡崎邸にはその主要な続き座敷の上に武器庫とした納屋が設けられているが、その床は下の階の天井と構造的に完全に分離されている。これは遮音と秘密のためと思われる。
岡崎邸のこれらの仕様は、縫製や建設、表現の細部まで規定されていた封建社会において、一般の武家屋敷では考えることの出来ないものである。彼の例外的な地位があって始めてこれら特殊仕様が実現したものと考えられる。