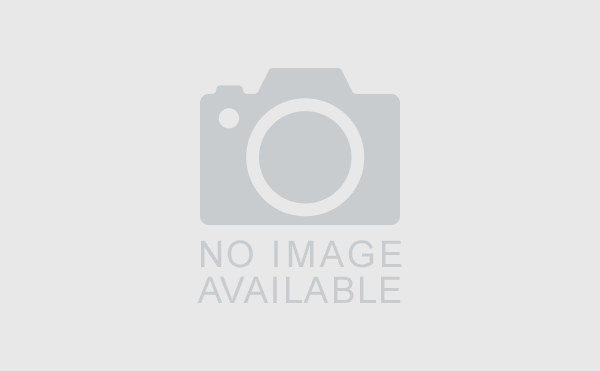何故に岡崎平内邸に特別の仕様が許されたのか? その3
なぜ、岡崎平内可之がかくも高く信頼されるようになったのか?
既に記述したように、岡崎平内家5代目の可之がこの肥大化した借金を短期間に解消させたからであるが、それはどのようにして可能となったのであろうか?
岡崎平内可之は、文化2年(1805)に家禄を相続した。兄、4代目岡崎平内(平蔵)が馬廻で家禄200石であったが、流行病であった疱瘡に罹り若くして(30歳)病没したので、商家に養子に出されていた弟、可之が父親3代目岡崎平内に急遽呼び戻され、兄の後を継いだ。しかし、嫡子でなく養子に出されていた弟が継承したことから家禄は150石に減額された。可之の父親、3代目岡崎平内は、宝暦3年(1703)に家督を相続し、郡奉行から安永8年には勘定頭となり、天明2年(1782)には禄高200石となり、天明8年には寄合となった出世頭であり、以降、家禄を継承した人物は、皆、平内と呼ばれるようになった。
可之、5代目岡崎平内は、文化8年(1811)に 江戸詰部屋番御膳奉行となったが、これは新人に交代で江戸詰の経験を持たせる鳥取藩の習慣的な人事と思われ、翌文化9年(1812)には鳥取に戻ったので、この間に彼が藩財政復興に直接係わったとは考え難い。。
可之が藩財政に影響する役割を果たすようになったのは、文化13年(1816)に御徒頭となった翌年、文化14年(1816)、日野郡の出鉄御用係となった時以来と考えられる。可之は、鳥取藩の上級武士、福田丹波の所領地、日野郡に派遣され、ここで行われていたタタラ製鉄の生産の合理化並びに需要先の開拓を行ったものと考えられる。鉄山師近藤家に先ず大坂に、次いで江戸に直販店を出し、更に日野ばかりでなく、日南とその他藩内全地域の鉄山師及び倉吉で開発された農機具にいついてもその販路の開拓を容易にするために境港に共同の金物売り場を開設した。これによって倉吉の鍛冶屋の生産が活発となった。
岡崎平内と倉吉淀屋の関係
しかし、タタラ製鉄を中心とした産業の振興のみで財政復興させるにはかなりの時間を要する。岡崎平内可之が藩財政復興を短期間で達成するためにはもう少し別の手段も平行して使ったように思える。
昭和16年(1941)5月刊の倉吉町誌に次のような逸話が記されている。
倉吉では、大坂淀屋が闕所とされる少し前,、恐らく元禄初期、淀屋が暖簾分けする際に、鳥取藩は、淀屋の番頭、牧田仁右衛門に藩に対して必要な資金を用立する交換として藩が生産奨励した産物を取扱う特権を与えた。
この逸話の筆者がどのような資料に基づいてこれを認めたのか定かでない。この一文は天保の飢饉(1732)との関係で書かれているが、大坂淀屋が闕所となったのが、宝永2年(1705)なのでその番頭が以前に岡崎家の小間使となったとするとそれは元禄の飢饉(1691-1695)、あるいはそれより前の天和の飢饉(1682)の頃のことと考えざるを得ず、想定されている逸話は時期が異なり、間違っている。もし、番頭が岡崎家の小間使であったことがあるとすれば、それは岡崎平内家の初代、岡崎平太兵衛、可之から見れば曾祖父の時期である。
しかし、岡崎平内可之が米相場で藩財政の穴埋めをしていたことは、前述のように江戸からの飛脚便が鳥取に着いた際に可之が大坂に出張していたということからも推測できる。とはいえ、彼がどのようにして大坂米市場の株仲間に入れたのかは不思議である。日本中に約400藩があり、どれだけの藩が米市場に直接出入り出来たであろうか?当時、米市場は株仲間制度で運営されていたが、藩の武士が商人のつくる株仲間の一人となるのは一般的ではなかったと思われる。可之が米市場の株仲間に入れたのは、何等かの縁故があったから可能となったものと考えられる。
ここで考えられることは、この大坂の米市場を築き、大変な財をなしたが、華美な生活をしたという理由で闕所となった淀屋の番頭、牧田仁右衛門が、淀屋から暖簾分けし倉吉に織物商を開店し、お陰で倉吉の町が活気づいたということはどうやら事実のようである。倉吉淀屋が創業当時、可之の曾祖父が便宜を図ったというような繋がりも全くあり得ないとは言えない。何故なら元禄期に倉吉に開業した織物商牧田が倉吉で生産された反物を大坂で売るのは藩の便宜なしには難しいと思われるからである。しかし、倉吉の織物商牧田は、やがて倉吉淀屋と名乗るようになり、大坂にも支店を出し、倉吉でも大坂でも繁盛したことは知られるので、時代は下るが、藩の財務元締、岡崎平内可之がこの倉吉淀屋の支援を得て、大坂米市場の株仲間に入れてもらったと考えることは可能であろう。
何と言っても可之は、算盤も出来、和算にも長けていたので、株仲間にも入れ、そこで米相場で利益を上げることが出来たとも考えられる。米相場はやや博打的な側面もあるので、相当優秀なアドバイザーが傍に居たものと考えられ、それは当時既に倉吉淀屋は大坂淀屋を出していたので、その支援を受けたのかも知れない。
何れにせよ岡崎平内は、これによって大阪で米相場によって短期に収益を獲得し、日野、倉吉の鉄産業の振興と併せて藩の財政危機を救ったように思える。
この結果、4年後の文政3年(1820) 在吟味役へと昇進し、翌年、銀札場御用となり、文政10年(1827)に元締め役、禄高200石に戻した。この頃、岡崎平内の住まいも、栗谷から馬場町に移されたようで、この移転の際には岡崎邸は家格にあった武家屋敷だったものと思われるが、家格の更なる上昇を見越した移転であったようにも思われる。
財政の元締め役が藩の財政にとって重要であることは、藩の大方の人が認めていたであろうが、岡崎平内がたたら製鉄と倉吉の鍛冶による農機具生産との連携で地域の活性化を達成したということは大方の家老には予測できなかったであろう。
文化14年(1817)、藩が岡崎平内可之を日野に派遣したのは通常の人事異動とも考えられるが、この異動は、当時、日野を管理していた禄高3500石の上級武士福田丹波の声掛であったかも知れない。福田丹波は、家老並みの禄高でありながら家老とはならず、誰も望まない僻地にある日野を所領していた。彼はここでたたら製鉄を振興し、藩内外での名刀生産を助け、経済的には比較的豊かであり、藩が困ると必要に応じて用立てしていた。岡崎平内可之はたたら製鉄の要点を福田丹波より伝えられたに違いない。岡崎平内可之がここで行ったのはたたら鉄を大坂や江戸に直送して販売する仕組みを整備したことと既に開発されていた竹製の千歯扱きを鉄製にし、たたら鉄の活用範囲を拡大したことに重要なポイントがある。ここにも福田丹波のアドバイスがあったかも知れない。藩の中で福田丹波のみは岡崎平内の優秀さと彼がもたらすであろう成果の大きさを期待していたように思える。
藩が困った時に相談するのは福田丹波であったので、可之の日野への人事異動は、福田丹波の提案であった可能性も考えられる。
たたら鉄の販路拡大、生産振興と鉄材を農機具とする新たな産業の起業は確かに藩財政の復興に効果があったと考えられるが、効果が生まれるまでにかなりの時間を要するように思える。
更に即効性があったのが、米市場であった可能性がある。藩主と泰姫との婚儀を伝える飛脚便が到着した折も彼は大坂に出掛けていたように元締めとなっても米相場で利益を上げていたようである。米市場は1730年(享保15年)には、江戸幕府公認の堂島米会所となっていたが、ここでは株仲間が公認されていた。株仲間は商人がつくった組織であるから鳥取藩の武士が簡単に出入りできるとは思えない。にも拘らず彼が米市場で利益を上げていたのであるからこの株仲間に入れるよう可之を支援した人物があったものと考えられ、それは倉吉大坂の両淀屋であったものと想像される。元禄期に藩が牧田仁右衛門等の織物産業を支援したお陰と言うべきかもしれない。
岡崎平内可之による藩財政の復興は、福田丹波、日野の近藤家や倉吉の牧田家などの協力者があって達成されたものと思われる。
この藩財政の復興は、可之の個人的な努力によって達成できた側面が多く、藩としては岡崎平内可之に任せただけなので藩にとって可之が極めて重要な人物となったものと思われる。