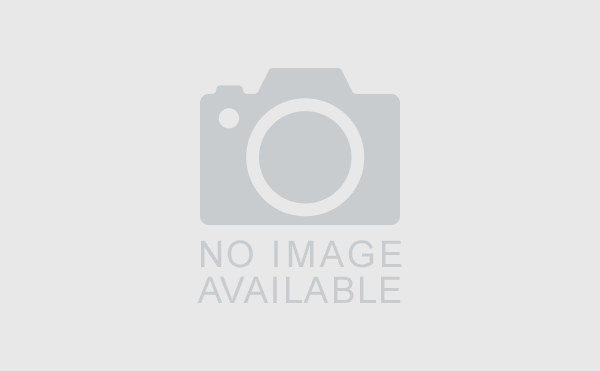何故に岡崎平内邸に特別の仕様が許されたのか? その2
岡崎平内は、藩財政の復興を見事に成し遂げ、文政4年には銀札場御用、文政8年(1825)には勝手方長となり、寄合、即ち藩の意思決定会議のメンバーとなり、更に文政10年(1827)には元締め役、即ち藩の財務総体の元締めとなった。
この時の禄高が50石加増され200石となったのだが、そもそも彼は岡崎家の末子であったので商家の養子となっていたが、兄、岡崎平内家4代平蔵が城務着任早々に病死したため商家との養子縁組を解消して家系を継ぐことになった。しかし、これが養子と判断され、家禄が50石引き下げられたので、文政10年(1827)にやっと先代の家禄に戻ったに過ぎなかった。
文政11年(1828)には昵近銀札場長役兼帯となった。昵近(じっきん)というのは、側役とも呼ばれるが、藩主の相談役のようなものである。銀札場長役は、藩札の製造管理をするいわば藩の金庫番長で、財政元締めがこれを兼務することとなり、藩財政はほぼ彼に一任されたことになる。このことは、藩の彼に対する信頼が極めて高かったことを示している。
この当時、藩主は、第10代池田斉稷(なりとし)であったが、彼は文政13年(1830)5月2日に江戸屋敷で死去し、その実子、池田斉訓(なりみち(9歳))が第11代藩主となった。天保2年(1831)、若き藩主斉訓が、将軍家斉の前で元服した際に将軍から側室、お瑠璃の方(青蓮院)との間に生まれた末子、泰姫(やすひめ(3歳))との婚約が提案された。(鳥取藩史)
鳥取藩の岡崎平内可之に対する信頼の高さを示したー国元を預かる留守番家老は江戸からの飛脚便を受取っても岡崎平内-可之の返答なしには藩の家老衆にその内容を伝えられなかったー
天保2年(1831)9月25日朝六つ時(午前6時)に9月16日に認められた江戸からの書状が飛脚便によって実質僅か8日間で届いた(家老日記天保2年9月25日)。鳥取藩江戸藩邸から鳥取城東門までは距離約670kmであるから84km/日という速度で送付された計算となる。姫路から鳥取の険しい山道を勘案すると大変速かったことになり、この手紙がどれ程急ぐ内容だったかが想像されよう。
この手紙を受け取った留守居の月番家老は、しかしながら、これを直ちに他の家老たちに知らせなかった。手紙の内容は、泰姫輿入れに関する報告であった。家老は、この内容が藩の財政にとって大変な出来事と判断した。家老は、かつて明和3年(1766)、5代目藩主重寛(しげのぶ)が桑名藩主の次女律姫を正室として迎えたが、婚姻後程なく死亡したため田安徳川宗武の四女仲姫を継室として迎えた。これによって藩財政が悪化し、鳥取藩は大坂の町人から借金せざるを得なくなり、この借金が見る見るうちに肥大し、藩財政を窮地に陥落させたことを知っていた。しかし、彼は、岡崎平内可之がこの肥大化した借金を短期間に解消させたことも良く知っていたので、先ずは藩財政の元締めの意見を聞きたかったものと考えられる。
鳥取に飛脚便が届いた折は生憎、元締め岡崎平内可之は大阪に出張中であり、3日後の9月28日に帰着した。月番家老は、可之帰還の翌朝可之を呼び出し、藩主の婚儀の件を伝えた。(家老日記)
岡崎平内可之は、「難有奉存旨御請申上恐悦申上候=ありがたくこの旨お請け申し上げ、謹んでお慶び申し上げます」と返事した。家老は、この答えを得て、安心してその日、9月29日の日付で家老の方々に通知した。9月25日に受け取った飛脚便の内容が家老に伝えられるまでに4日を要したということは一般にはあり得ない異常なことであり、このことは、可之に対する藩の信頼度・依存度の高さを明白に示している。