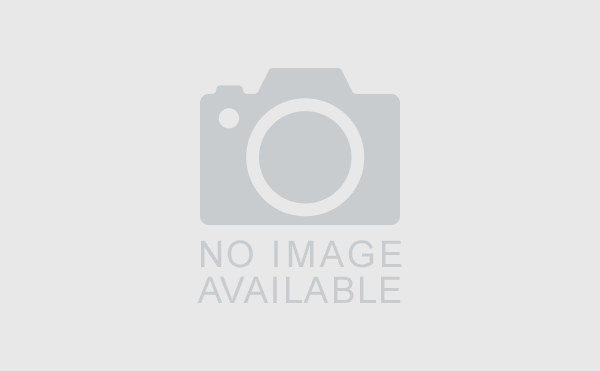岡崎平内が目指し、実践した議会制民主主義の下での地方振興
岡崎平内が鳥取県再置を実現できた理由
鳥取県は、島根県に併合され、一旦消滅したが、復活した。
この功労者の一人に岡崎平内がいる。
もう一人の功労者としては、足立長郷氏がいる。
この二人の活動形態は、大きく異なる。
足立長郷氏は、共斃社を設立し、廃藩置県によって失職し、貧困に喘ぐ旧武士を鼓舞し、種々の直接的な行動を行った。
その弁舌は鮮やかで、多くの士族の共感を得たが、その活動は、次第に凶暴性を帯び、逆に一部の市民から嫌われるようになってきた。
これに対して岡崎平内は、2つの方法を取った。
第一の方法は、島根県から委託された日野郡長を辞して島根県会の議員に立候補し、旧鳥取県内の人々の支持を得て議員となった。
議員となった岡崎平内は、議事運営細則を提案し、それを成立させた。
議事運営測を成立させた岡崎平内は、島根県会の信を得て、明治14年3月、島根県会第2代目の議長に推挙され就任した。
岡崎平内が提案した議事運営細則は、大変ユニークなもので、平等な社会を築くことに特別の配慮がなされていた。
議題毎に議員を3つのグループに無作為に分け、その内部で議題について討議し、それら3者の結論を突き合わせることで、賛否が必ず決まるように考えられている。
1つの議題について議会を3回開催する。
1回目は、議題として採用するか否かを判断する議会とし、ここで議案に修正すべき点があれば、議長が修正を担当するグループを指名する。
2回目は議題を逐条解釈する議会であり、修正する必要があるとされた議題については議長が指名したグループによる修正案について、逐条議論する。
3回目は議決のための議会である。この議決の際に修正案がある場合には先ず修正案について議決し、これが否決された場合には当初の議案について議決する。
このように議員は、出身や職業などの背景に囚われずに平等な立場で議論し、結論を効率的に導くことが出来るように工夫したものであった。
これは、島根県の広範な地域から選ばれた議員たちから高い評価を受け、このことから岡崎平内は全ての議員の総意として議長に選出された。
岡崎平内は、第2の方法として、このような島根県会での活動と並行して旧家老や旧藩士ばかりでなく、
主な町人、農民にも呼び掛け、愛護会を設立した。ここでは鳥取の人々の窮状を救うための活動方針を検討し、種々の産業を興すと共に旧藩主の支援で生まれた「共立社」の中で各種の互助会と共立学舎という学校で人材の育成を行おうとした。
産業振興が第一で自宅の脇に所有していた江崎町の土地に機織場をつくり、養蚕と絹糸の生産と平行して布地の生産を行うなど、堅実な産業の振興を行った。このような地方の産業の活性化のためには県の支援が欲しかったが、相談に行くにしても鳥取から松江は遠く、鳥取の自治を確立する必要性を感じ、そのためにはどうするべきかを検討していた。
折しも、東京で産業振興の助成を得るために鳥取に縁のある人々を訪ねていた愛護会のメンバーが、旧鳥取県2代目の県令であった関義臣氏から「国政の逼迫した状況とその打開のためには地方の再興が急がれ、鳥取県の再置はそのような意味で重要である。」との時世に対する私論を聞かされ、愛護会の活動方針が鳥取県の再置ということで明確になった。
以降、愛護会は、鳥取県再置嘆願書の作成と政府要人への支援の依頼を積極的に推進することとした。
島根県会の議長となった岡崎平内は、島根県令の信をも得た。愛護会の鳥取県再置嘆願書には批判的であった島根県令、境二郎、は、明治14年5月10日に松方内務卿宛に、「島根県は鳥取の人々を差別するようなことはしておらず、平等な県政を行っている」との意見書を提出していた。しかし、境二郎は、岡崎平内と愛護会メンバーの陳情を受け、彼らの「鳥取には島根や出雲とは異なる長い歴史があり、例え平等な行政を行っているとしても受け取り方が異なり、鳥取のためにはならない」という主張に納得し、明治14年5月22日に書記官を上京させ、再置建議書を内局に上申した。島根県令、境二郎は、僅か12日間で翻意したことになる。
この上申書が功を奏し、明治14年8月、山形有朋による島根県巡視の実現を見た。その山形有朋は、岡崎平内を筆頭とする愛護会メンバー、足立長郷等の共斃社のメンバーと面接した後、島根県令、境二郎とは長時間にわたる討議を経て、「島根県を割って鳥取県を置くことが急がれる」という趣旨の報告書を認めた。これに基づいて伊藤博文によって鳥取県再置案が草稿され、これが参議会で承認され、明治14年9月12日、鳥取県再置が実現した。
この間、岡崎平内等、愛護会が乗り越えねばならなかった第一の障害は、松田道之、東京府知事であった。彼は、鳥取藩家老、鵜殿の家来の子息であったが、尊皇攘夷運動に深く係わり、維新後、内務官僚となり、琉球処分官としての働きが認められ、明治12年、東京府知事となっていたが、明治8年より内務大臣の補佐役で内務省ナンバー4の高等官僚、大丞(たいじょう)となっており、明治9年の鳥取県の島根県への併合を提案・実施した張本人であった。岡崎平内等は、彼と長時間にわたって討論し、最終的に松田道之は「地方振興なしに国家の繁栄なし・地方振興には地方自治が重要」という岡崎平内・鳥取愛護会の主張に納得し、鳥取愛護会の活動を妨げないという合意が得られた。
残る大きな障害は、凶暴化した共斃社の活動に怯えた伯耆、但馬、汗入久米等の人々によって鳥取県再置反対運動が生まれたことであった。しかし、これらの再置反対運動は、一つにまとまることなく、提出された建白書も個人名のものに留まった。
他方、明治政府には再置を支援する空気が濃かった。先ず、皇族たちが鳥取の味方をした。因幡八上采女(いなばのやかみの うねめ)、因幡国造浄成女(いなばのくにのみやつこ きよなりめ)といった古代の采女(女官)の話しもあるが、大正天皇の生母、二位局(にいのつぼね)、柳原愛子(なるこ)は、明治天皇の側室であり、公卿日野家の嫡流、柳原家の娘である。柳原家は法美郡百谷(ももだに)に所領を有し、その経営を行い、頻繁に訪れていた。また、明治天皇の高祖父に当たる光格天皇は、東山天皇の孫、閑院宮典仁親王(かんいんのみや すけひとしんのう)と倉吉の荒尾志摩家の家臣の娘、大江磐代(いわしろ)との間に生まれた。大江磐代の母は、倉吉の鉄問屋の娘、おりんである。これらのことから、天皇家と鳥取の関係は深く、明治政府を構成する皇族は、鳥取に特別の親近感を抱いていたので、鳥取県の再置に肯定的であった。
以上のことから岡崎平内と愛護会の鳥取県再置活動は成功裏に終わったが、中でも岡崎平内の提案による議事細則が高く評価されたがために彼が議長に選出され、それが故に島根県令、境二郎も岡崎平内の意見に納得し、島根県令から鳥取県再置が上申されたことが最も大きな効果をもたらしたものと考えられる。